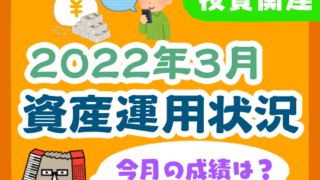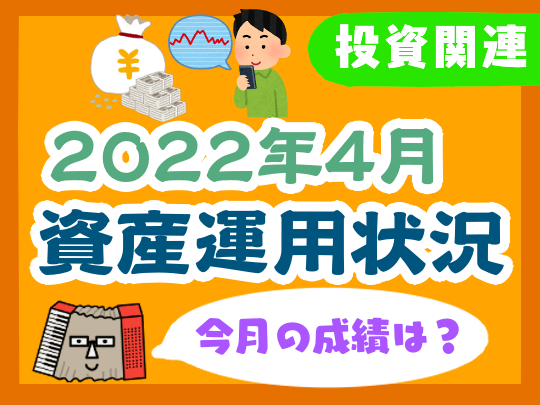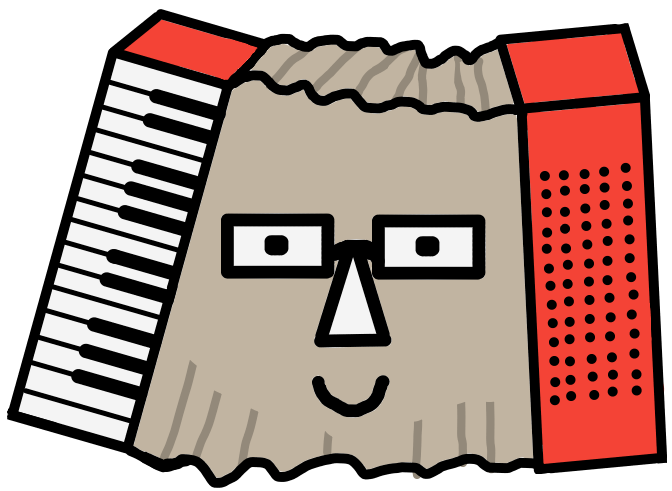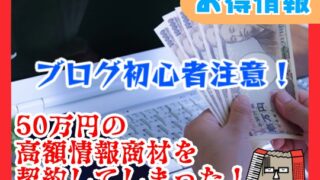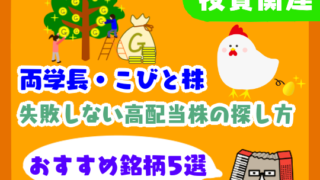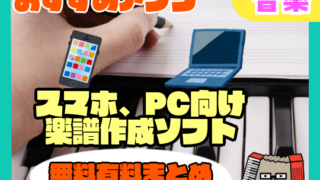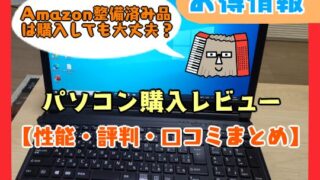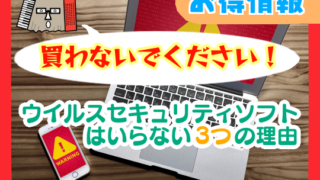あなたの家計資産は誰が管理していますか?
我が家は30代の夫婦2人暮らしで、家計の資産管理は夫の私に一任されています。
30代と言えば、お金の管理が気になりだして、株や債券などの金融資産を購入したくなる人が多くなってきます。
すでに資産管理をしている同じような30代夫婦の方達は、他人の家計の資産状況が気になりますよね?
そこで、我が家で行っている資産運用状況を報告して、現在投資をしている方、これから投資を始める方に参考になるように、できるだけ細かく書きました。
前半では株式を、後半では投資信託、住宅ローンについて書いているので、最後までご覧になって、是非ともあなたの家計の参考にしてみてください!
こんな方にオススメ!
・30代から投資を始めた方、これから投資を始めたい方
・他人の家計の資産状況を知りたい方
・住宅ローンが気になる方
よろしければ先月の資産運用状況も併せてご覧ください。
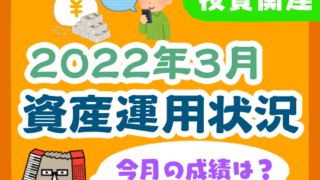
投資先紹介
・株式
■メイン口座(SBI証券)
中長期保有銘柄・優待銘柄
■高配当ポートフォリオ(SBIネオモバイル証券)
高配当銘柄
・投資信託
■積立投資(楽天証券)
・米国株式(S&P500)
・全世界株式(オール・カントリー)
・先進国債券
・ゴールド(為替ヘッジあり)
投資先は大きく分けて3つに分けています。
株式
■メイン口座(SBI証券)
・成長株やバリュー株を中長期で保有。
・半分以上は優待銘柄。
保有内容はこちら※
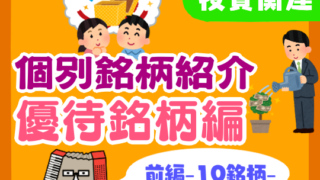
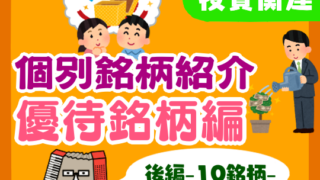
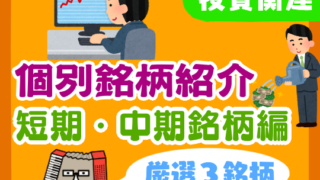
※2021年5月12日時点での内容です。最新の保有内容は今回の記事にて紹介しています。
■高配当ポートフォリオ(SBIネオモバイル証券)
高配当の恩恵を受けるためには、米国株を購入するのが一般的です。
ですが、この口座で購入しているのは日本株となっています。
理由としてはSBIネオモバイル証券は1株からの少額で購入できるので、取得単価が高い大型株でも手を出しやすくなり、高配当の銘柄を何種類も分散して購入できるので、この口座を活用しています。
もう一つの理由としては、米国株は日本円で投資していたとしてもドルに変換されるので、購入する際と売却する際の為替によって投資額の変動幅があります。
海外に移住するならドル建ての投資でも良いでしょうが、私は今後も日本で暮らす予定なので、得られる配当金は日本円である方が都合が良いです。なので、日本円で配当を受け取れる日本株に投資する事も悪くない選択肢だと思います。
分散しすぎると管理が面倒にはなりますが、基本的には月1回のチェックで良いので、そんなに手間は掛かっていません。
このポートフォリオの作成は、両学長・こびと株さんの推奨している方法です。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
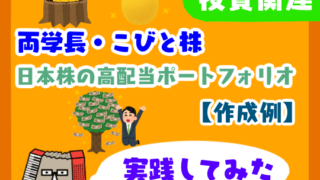
投資信託
■積立投資(楽天証券)
つみたてNISAを利用しつつ、毎月積み立てで投資信託を購入しています。
おおよその比率は以下の通りです。
○夫口座
株式(S&P500指数連動型)80%、債券10%、ゴールド10%
○妻口座
株式(全世界型)100%
投資状況実績
中長期・優待銘柄(SBI証券)
・夫口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |
| 4,714,400 | +767,800 | -230,450 |
・妻口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |
| 2,236,550 | +620,950 | -77,100 |
感想・反省点
二人の口座を合計して、先月より-約30万円となりました。
今月は新たに売買をしていませんが、株式市場全体が下落相場となってるようでした。
ポートフォリオ全体では損益となりましたが、これくらいの変動率は許容範囲ですね。
個別株の多くは株式優待を目的としているので、優待が貰える限りは株価はあまり気にしていません。
優待関係で言うと、4月末までの保有で、コーア商事HDからプライム市場に移行記念の記念優待が貰えることになりました。
夫、妻口座で保有しているので、1,000円×2=2,000円分のQUOカードが貰えます。
今月でコーア商事は一時的に3倍株にまで成長してくれたので、ポートフォリオの成績は良くなかったですが、結果的には満足です。

高配当ポートフォリオ(SBIネオモバイル証券)
| 毎月積立額(年間積立額50万円÷12ヵ月) (円) |
| 41,666 |


| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) | 配当利回り(%) |
| 1,198,781 | +115,044.4 | -11,983.7 | 4.35 |
感想・反省点
1銘柄を新規購入しました。
ヒューリック(3003)
・オフィス・店舗・商業施設などのビルを主に扱う不動産業
・不動産業の時価総額順位 4/56社
・営業利益率20%台で営業収益も右肩上がり。
・過去10年の累進配当。
上記の理由から新規購入。
個別株のポートフォリオは全体的な下落でしたが、高配当株の下落率はそこまで大きくなく、小幅な減益となりました。
高配当株の特性として、ほとんどの投資家は配当金が目当てなので、あまり売買をすることもなく、逆に下落相場に買い増す人が多いので、急落することは少ないです。
今は配当金を再投資していますが、配当金を貰うつもりの数十年後までは、株価が下落してくれる方が安値で買えるので、「むしろもっと下落しても良いんだよ?」とも思っています(^_^;)
積立投資(楽天証券)
| 毎月積立額 | 夫口座(円) | 妻口座(円) |
| 50,000 | 10,000 |
・夫口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |
| 818,811 | +64,811 | -35,281 |
・妻口座

| 合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |
| 470,785 | +27,452 | -29,730 |
感想・反省点
米株も全体的な下落相場だったので、米株を中心としたS&P500や全世界株ファンドも下落しています。
妻の口座で間違えて購入していた「受取型」で購入した全世界ファンドは、損益がプラスになっていたので売却しました。
保有していても問題無かったんですが、口座の管理をする上では少し面倒だったので、除外しておきました。
住宅ローン
2019年に35年ローンでマンションを購入。(3,700万円の借入)
| 借入残高(円) | 住宅査定額(円)※ | 差額 | 金利(%) | 完済予定(年) |
| -34,757,270 | 33,000,000 | -1,757,270 | 0.505 | 2054 |
※査定日2021年4月(机上査定)にて査定額3,300万円の査定額より。
2019年に35年ローンでマンションを購入しています。現在の年齢からすると、リタイヤ前後くらいで完済予定です。
今のところは住宅を売るつもりはありませんが、突然仕事が無くなったり、収入が安定しなくなる事態になったときは売却しないといけない場合もあります。
そのために、常に自分の住宅価格を知るため不動産屋にて査定をしてます。
差額を現在の貯金や金融資産で賄えない程度である場合は、住宅を売却した際に借金が残る事になるので、事前に把握しておきましょう。
上記の査定額は机上査定ではありますが、ある程度の参考にはなるので、 住宅を購入している方は一度、査定をして貰うことをおススメします。
分譲マンションの場合でしたら、手軽に査定できる「マンションマーケット」というサイトを利用する事をオススメします。自分の住んでいるマンション名で検索すると大体の査定額と将来の予想価格が分かるので、とても参考になります。
持ち家の場合、「イエウール」というサイトから申し込むと、複数の不動産会社から査定をして貰えるので、合い見積もりができて非常に参考になります。
私はイエウールにて机上査定を申し込みましたが、不動産会社と電話やメールで数回程度のやり取りをしなくてはいけないので少し手間ではありますが、複数社から見積もりがあり、会社によっては数百万円も査定額に差があったので、相場観を知るには良い方法だと思いました。
同じような理由で、いま会社を辞めたら退職金がいくら貰えるかを計算しておくのもおススメです。
今月のマンションマーケットでの査定額
3,250万 〜 3,420万円(平均3,335万円)
前月比:±0万円
今月からマンションマーケットでの査定額も記録する事にしました。
前回の机上査定から1年経ちましたが、推定評価ではマンション価格は値上がりしているようです。
実績まとめ
| 総合計 | 評価額(円) | 含み損益(円) | 前月比(円) |
| 9,439,327 | +1,596,057 | -384,545 |
感想・反省点
先月から-約40万の含み減益となりました。
今月のトピックとしては、加速する円安ドル高、FRB(米連邦準備制度理事会)が一段と利上げの姿勢を積極化するなどの要因が大きかったです。
金利が上がる → 預金にお金を回したい → 株が売られる
こういった流れから、一般的に金利が上がると株価が下がります。
円安ドル高の場合は、ドルの価値が上がることで、海外からすれば日本の商品がバーゲンセール状態になります。
なので、輸出を主な収入源にしている海外向け企業にとっては業績が好調になりますが、逆に海外製品を輸入している企業にとっては円の価値が下がる事で実質的な値上げとなっていまいます。
一般的には円安の方が株価は上がりやすいですが、ロシアウクライナ情勢の長期化によって、エネルギ―など多数の分野で商品の値上がりがあり、うまく価格転嫁ができていないことで、業績が優れない企業が多かったようです。
アメリカ市場では金利上昇による株価低迷が主な原因ですが、アメリカ市場と日本市場相関関係があるので、円安が続く限りは日本株も冴えない値動きになるかと思います。
現在ブログを執筆中の4月28日では、一時的に1ドル130円まで円安になりましたが、これは20年ぶりのことです。
今や140円や150円まで加速するのではないかと予想されていますが、株価以上に為替を読むことは困難なので、一般的な個人投資家にとっては、粛々と積立投資をすることが最適解でしょうね。
先月の資産運用状況もよろしければ参考にしてみてください♪